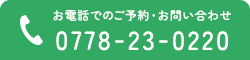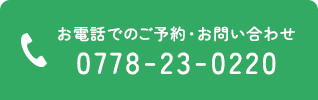認知症カフェ こころとは…
 認知症の方とその家族、地域住民の方など誰でも参加できる集いの場です。
認知症の方とその家族、地域住民の方など誰でも参加できる集いの場です。
参加者の皆さんで温かいコーヒーなどを飲みながら、団らんや情報交換、レクリエーションなどをしながら楽しい時間を一緒に過ごしませんか。
お待ちしています。
| 対象 | 認知症の方とその家族、認知症に関心のある地域の方 |
|---|---|
| 日時 | 毎月第2・第4木曜日(平成26年9月より)13時〜16時 ※途中入退場は自由 |
| 料金 | 100円(茶菓代) |
| 場所 | 月岡医院(〒915-0811 福井県越前市本多1丁目10-18) |
| お問い合わせ | TEL:0778-23-0220 担当:山本、恵美 |
| お知らせ | 最新のご案内はこちらに掲載します |
認知症カフェ7つの要素

- 認知症の人が、病気であることを意識せずに過ごせる。
- 認知症の人にとって、自分の役割がある。
- 認知症の人と家族が社会とつながることができる。
- 認知症の人と家族にとって、自分の弱みを知ってもらえていて、かつそれを受け入れてもらえる。
- 認知症の人とその家族が一緒に参加でき、それ以外の人が参加・交流できる。
- 「人」がつながることを可能にする仕組みがある。
- どんな人も自分のペースに合わせて参加できる。
認知症カフェの効果
本人に対する効果
認知症の人と家族の両方への効果
①認知症の人と家族が同じ空間で出会いつつもそれぞれの横のつながりを形成し強化する場となっている
②食事をするという基本的欲求を満たし、おいしさを介して元気をもらう場となっている
認知症の人本人に対する効果(認知症の人の心身を満たすことによる効果)
③コーヒーを飲んで一服できるスペースがあったり、話を聞いてくれる人がいたりすることで、認知症の人が明るく笑顔になれる場となっている
④認知症の人が様々な人と出会い、生きがいを感じられたり、懐かしいものにふれたりすることで症状の進行を緩やかにすることが期待できる場となっている
⑤認知症の人が民家などを利用した親しみやすい空間で自由にすごし、リラックスできる場となっている
認知症の人と社会がつながることによる効果
⑥認知症の人が社会的つながりや役割を得てやりがいを感じることで笑顔になり、生き生きと過ごせる場となっている
⑦認知症のために閉じこもりがちとなった人が他者との会話や趣味的活動を通じてまだできることがあると発見し自分らしさを取り戻せる場になっている
⑧認知症の人が地域で暮らし続けられるための居場所になっている
⑨施設に入所している認知症の人がくつろぎ、社会との接点を持つ場となっている
認知症の人とケアが出会うことによる効果
⑩若年性認知症や認知症初期で既存の介護保険サービスになじめない人や認知症と告知されていない人、認知症の病識が不十分な人の支援の場となっている
⑪認知症ケアの入り口となり、行政のサービスにつながる場となっている
⑫認知症の人が軽度の時から関係をつくることでその人の気持ちを理解した適切で継続的なサポートができる場となっている
家族や地域に対する効果
介護する家族同士が出会うことによる効果
⑬介護する家族が悩みや思いをはきだし泣くことで、明るくなることができ、安心感が生まれる場となっている
⑭介護する家族が仲間に出会ってつらいのは自分ひとりだけではないということを実感し、仲間づくりにつながる場となっている
⑮介護する家族同士が語り合うことで、実体験に沿った介護の工夫を学び取る機会となる
介護する家族と認知症の本人が出会い直すことによる効果
⑯介護する家族が本人と離れて息抜きできる安らぎの場となっている
⑰介護する家族が本人のよい状態を見ることで、穏やかになり認知症の人との間の緊張感が緩和される場となっている
⑱介護する家族が認知症の人の普段と違う姿や第三者の認知症の人への関わり方を見て理解を深める場となっている
⑲認知症の人を抱える家族が家族としての機能を維持するために家族内で認知症についてオープンに語るきっかけを与える場となっている
認知症の人と離れて暮らす家族にもたらす効果
⑳認知症カフェに認知症の人が通うことで遠く離れた家族も安心できる
介護する家族が専門職と出会うことによる効果
㉑介護サービス等の情報を家族が気軽に得られる機会となる
地域住民と認知症の人が出会うことによる効果
㉒地域住民にとって認知症を自分の近い将来のこととして身近に考える雰囲気が生まれるきっかけとなる
㉓地域住民が認知症の人と出会い、同じものを飲み、食べ、会話することで認知症が特別な病気でないことを知る場となっている
㉔認知症の人と地域住民が出会い、交流する場になっている
地域住民同士が出会うことによる効果
㉕世代や障害を越えた住民同士が生活の一場面として交流し、横のつながりが形成される場に なっている
㉖地域住民が誰でも立ち寄れるくつろぎの場となっている
支援者や社会に対する効果
支援する医療・介護専門職への効果
㉗医療・介護専門職が認知症の人の強みに気づき、自身の認知症ケアを振り返る場となっている
㉘医療・介護専門職が地域住民や地域で暮らす認知症の人と出会うことで認知症ケアを通した 地域づくりを考えるきっかけとなる
㉙医療・介護専門職と介護する家族・認知症の人が同じ立場で交流できる場となっている
支援する市民ボランティアへの効果
㉚市民ボランティアが認知症の人とかかわることで理解を深める場となっている
㉛市民ボランティアが効果を実感し、喜びややりがいを感じる場になっている
社会や地域への効果
㉜地域包括支援センターや社会福祉協議会などの関係団体に活動が伝わることで、地域のネットワークづくりや連携強化につながる
㉝誰でも集える場となることでコミュニティの雰囲気を明るくする
㉞マスコミに取り上げられることで社会全体の認知症への注目を集める